働き方改革成功のためのアイデアを3つの視点から紹介。仕組みと意識の変革が重要
少子高齢化による働き手不足、長時間労働による健康被害、雇用形態による格差など様々な問題を解決し、労働生産性を高めるには、働き方改革を実現し、柔軟な働き方を選択できるような社会に変えていく必要があります。
しかし、働き方改革によって企業や従業員が恩恵を受けるには、法改正に対応するだけでは不十分です。また、これまでの働き方や意識をすぐに変えるのは簡単ではありません。そこで今回は、働き方改革を成功するために活用できるアイデアを紹介します。
目次
働き方改革の目的
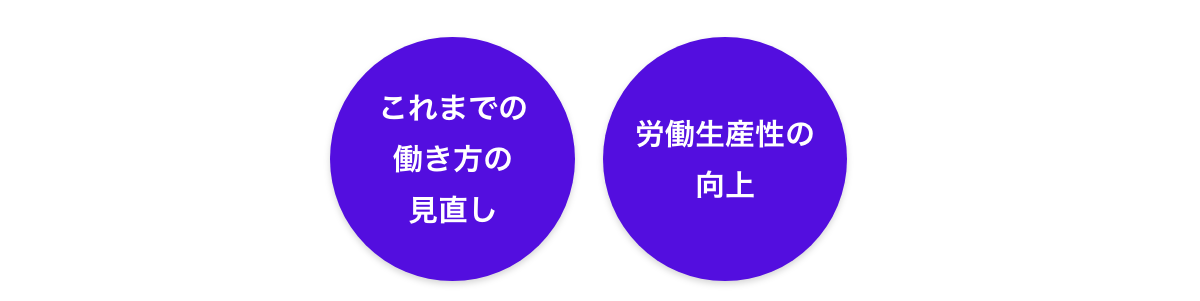
改めて、働き方改革はどんな背景や目的で推進されるのかを整理します。働き方改革の意義や効果を、経営層だけでなく従業員も理解した上で取り組むことが重要です。
これまでの働き方の見直し
日本では「長時間働くこと」が評価される風潮があり、長時間労働の常態化、有給取得率の低さが課題となっています。時間外労働が増えるほど様々な疾患のリスクが上昇すると言われており、過労死や、うつ病など精神疾患が社会問題化しています。
また、長時間労働前提の働き方は育児や介護との両立を困難にします。そのため、ワークライフバランスの悪化や、キャリアの断絶が起きる要因となっていました。
今後、少子高齢化が進行し働き手が不足する中で、労働人口を増やすには、多様な働き方を選択でき、プライベートと両立が可能であることは不可欠なのです。
労働生産性の向上
長時間労働と関連し、日本企業の問題となっているのが労働生産性の低さです。生産性が低いため長時間労働が必要になったり、効率性を軽視してダラダラとした働き方となっている企業は少なくありません。
企業の利益率を高め、競争力を持つためには効率的な働き方に変わっていく必要があります。
働き方改革実現には制度のみでは不十分

働き方改革のスタートによって、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金をはじめ、関連する法律の改正や追加がおこなわれました。
罰則をともなうものもあり、企業は対応が必要になります。
しかし、制度を整備しただけでは効果的な働き方改革を実現することは困難です。
運用が成功しないと形骸化してしまう
働き方改革実現のために、制度導入だけでは不十分である理由は、現場で運用できないと形骸化してしまうことです。
具体的には、
・虚偽の勤務時間申告による隠れ残業や持ち帰って仕事をし、労働時間が減らない
・在宅勤務制度が整っているのに、社内の空気から利用できない
などの状況が考えられます。
このような問題が起こる理由は、制度の趣旨や目的を現場が理解していないこと。また、これまでの評価制度や従業員の価値観から脱却できないことなどが挙げられます。
制度が機能するためには、
・勤怠管理や評価制度などもあわせて変更する
・ワークフローの見直しを図る
・管理職・従業員が働き方改革の目的を共有し、実践するために協力する
ことが不可欠なのです。
企業により状況や優先課題が異なる
働き方改革を先んじて実践し、効果を上げている企業は少なくありません。他社の取り組みやアイデアを参考にすることは重要ですが、企業によって働き方や課題は多様です。
たとえば、業務量が多く人手不足により残業時間が多い企業と、ダラダラ残業や生活残業が横行し、従業員の労働生産性についての意識が低い企業では取り組むべきアプローチが異なります。
具体策を考える前に、自社の状況と課題を整理し、優先度と取り組みのしやすさを検討しながら進めていく必要があります。
従業員を巻き込んで実現する必要がある
働き方改革実現のためには、トップダウンによって従業員のワークスタイルを強制的に変えることも必要です。しかし、現場では異なる運用がされていたり、従業員のモチベーションが下がってしまい、効果を発揮しないケースは少なくありません。
経営層は働き方改革によって、会社の持続的な成長と従業員の働きがい創出の両立を目指さなくてはいけません。そのためには、働き方改革の実現で働き方や暮らしがどう良い方向へ変わっていくかを共有し、同じゴールを目指して推進していく必要があるのです。
残業時間を減らすアイデア
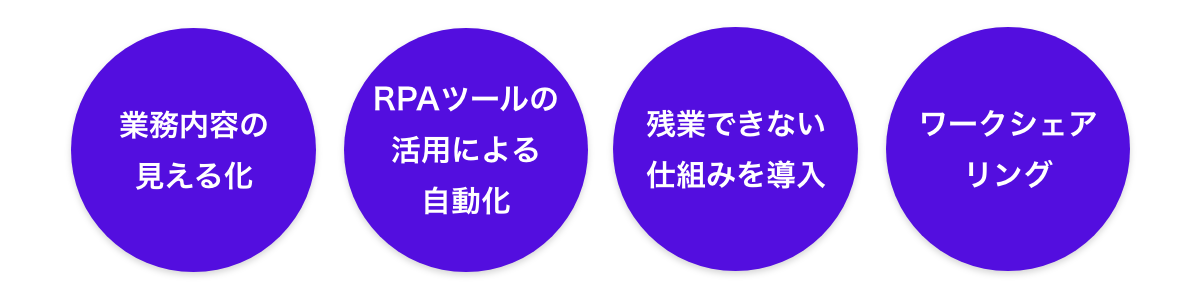
働き方改革を実現するために、企業が取り入れたいアイデアを紹介します。
まずは特に重要度が高い、残業時間の削減に活用できる4つのアイデアです。
残業時間を減らすには、制度だけでなく働き方の見直しが不可欠です。時間外労働が発生する原因を特定し、解決策を実施していきます。
業務内容の見える化
時間外労働を減らすためには、就業規則や社内ルールで制限をかけるだけでは不十分です。特に業務量が多く残業や休日出勤を余儀なくされている場合、隠れ
残業や従業員のモチベーション低下につながる可能性が高くなります。
残業時間削減に効果を発揮するのは、業務の効率化です。
RPAなどの自動化ツールを利用する、無駄な資料作成や承認業務を減らすなど、ワークフローの改善で業務時間を短縮することが残業抑制につながります。
【具体的なアイデア】
・業務内容と工数をリストアップする
・各自が利用しているフォーマットを統一する
・社内会議の頻度と内容の見直し
・稟議や決裁の流れ、権限を見直し
業務の必要・不要と優先順位を明確にすることで、働き方改革の目的の一つである時間あたりの生産性向上につながります。
RPAツールの活用による自動化
受注管理や経理処理など、定常業務に使う時間を削減し、複雑で付加価値の高い仕事に集力することも、労働生産性の向上につながります。
特に定常業務に追われがちなバックオフィス業務は、RPA(Robotic Process Automation)による自動化を検討すべき内容です。
RPAとは、人がおこなってきた定型的な業務をソフトウエアのロボットにより自動化するものです。
業務内容の見える化の中で自動化できる業務を発見し、必要なシステムを導入しましょう。
残業できない仕組みを導入
働き方改革関連法の改正により、時間外労働への規制が厳しくなりました。
残業が慢性化している組織では、前提とした働き方になっているケースが少なくありません。残業代稼ぎや、定時に退社しにくい空気があるなど理由は様々ですが、「不必要な残業をさせない」仕組みを導入することでタイムマネジメントの意識を植え付けることができます。
【仕組み例】
・残業の事前申請ルールを厳格化する
・強制的にパソコンをシャットダウンするシステムを導入する
・ノー残業デーを作る
・遅い時間の会議をなくす
・1回の会議時間を制限する
ワークシェアリング
ワークシェアリングは、その名の通り仕事を複数人で分担することを指します。
長時間労働改善のためにワークシェアリングが効果的な理由は、特定の人に業務が集中することを避けられるためです。
働き方改革で解決すべき事項として、時間外労働だけでなく有給取得率の低さも問題となっています。業務を他に任せられないため休めない状況を改善するためにもワークシェアリングは効果を発揮します。
また業務の属人化を防ぐことで、引き継ぎや教育が円滑になるメリットもあります。
【具体的な施策】
・属人的な仕事のやり方を見直し、チーム体制に変更する
・書類のフォーマット化により、誰が担当しても同じアウトプットが得られるようにする
ワークライフバランス実現のアイデア

働き方改革では、それぞれの人が個々の事情に応じ、多様で自由に働き方を選択できることを目指しています。そのためには、企業側が制度やインフラを整えることが不可欠です。従業員のワークライフバランス実現のための3つのアイデアを紹介します。
在宅勤務やテレワークの推進
コロナウイルス感染症拡大により急速に拡大した在宅勤務・テレワークは、ワークライフバランス実現のために効果的な対策の1つです。
不要な出社を増やすことで、通勤時間が不要となり家事やプライベートな時間を増やすことができます。
また、住む場所の選択肢も広がるため、家賃の安い場所に引っ越しリビングコストを下げたり、広い家に住み替えたりすることが可能です。
働く場所や時間の選択肢が増えることは、働き方改革が目指す自由で自律的な働き方と方向性が合致します。
フレックスタイムの運用
フレックスタイム制は、労働者が始業・就業時間や労働時間を自分で決定できることで、仕事とプライベートの両立を可能にする仕組みです。
子どものお迎えや、平日日中でないと対応が難しい手続きなども勤務時間の調整により可能となります。これによって、育児や介護との両立が難しく仕事を続けられない状況を避けることができる、時短勤務や早退により給料が減ることを避けられるなどメリットがあります。
また、閑散期と繁忙期がある仕事の場合は、余裕があるときに勤務時間を少なくすることで、総労働時間を減らし、過重労働を避けることも可能になります。
有給休暇を取得しやすい仕組み
厚生労働省がおこなった「就労条件総合調査」によると、2019年の有給休暇取得率は52.4%となっています。有給休暇取得率は年々改善傾向にあるものの、海外と比較すると低い水準で推移している状況です。
有給休暇の取得が進まない理由は大きく2つあります。
1つ目は、業務量が多かったり、他に担当者がいないことで休みにくい体制となっていること。2つ目は、休める状況であっても有給を取りにくい風潮があることです。
働き方改革実現のため、企業は従業員が有給休暇を取得しやすいように仕組みを導入する必要があります。
【具体的な施策】
・全社での計画年休の設定
・半日、時間単位で取得を可能に制度変更
・有給取得推奨日の設定
・有給取得状況の見える化
・連続休暇を取得した場合にインセンティブを支給
従業員を巻き込むためのアイデア
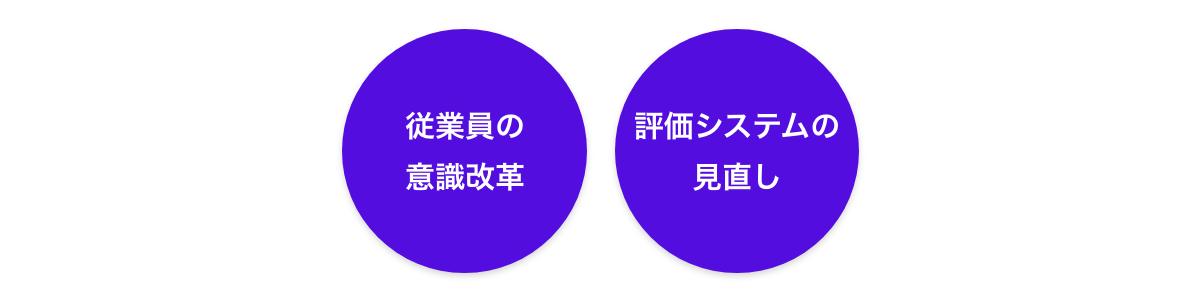
働き方改革を実現するためには、トップダウンの施策だけでなく、従業員を巻き込んだボトムアップの改善も不可欠です。
企業は従業員がモチベーションを維持しながら、主体的に働き方改善に向けて動く仕組みを整える必要があります。
従業員の意識改革
業務効率を向上させるには、一人ひとりが無駄な仕事を減らし、効率的に働こうと意識することが必要です。
時間外労働が減ることで、残業代が減り手取りが減少してしまう。家に帰るより会社で働きたいなど、従業員の意識が古い働き方のままでは全社での取り組み効果が薄れてしまうのです。
企業は働き方改革の目的、会社と従業員双方へのメリットを伝えることで、効率的な働き方を推進していく必要があります。
従業員一人ひとりが主体的に行動することで、働き方改革実現が近づきます。
評価システムの見直し
働き方改革の実現を阻害する要因の1つが、「労働時間が減ることで評価が下がるのではないか」という意識です。
これまで日本企業の多で「長く働く=頑張っている」と評価する風潮がありました。しかし、実際は労働生産性が低く、ただ長く働いているだけというケースは少なくありません。
特に直属の上司やチームに長時間労働を正当化する傾向がある場合、本人は効率的に働きたくても、残業を余儀なくされることが起こりえます。
評価の基準が労働時間ではなく成果に徹底することで、残業時間を減らす、有給を取得するモチベーションにつながります。
まとめ
働き方改革を実現したいけれど、何をすればいいかわからない企業は今回紹介したアイデアを参考に、自社へどのように導入できるか考えてみてください。
施策が効果を発揮するには、単にアイデアを取り入れるだけでなく、自社の状況を分析した上で、最適な活用をおこなうことが不可欠です。
また、経営層、管理職、従業員が目線を合わせ、働き方改革実現に向かって足並みを揃えて取り組んでいく必要があります。
関連記事
働き方改革とは
一億総活躍社会の実現を目指し、2019年にスタートした「働き方改革」。労働基準法をはじめ、関連法の改正がおこなわれ順次施行され、企業は働き方改革に対応するため、社内規定の変更や労働環境の改善をおこなう必要があります。 企業が働き方改革を実現し、業績向上へ役立てるためには、目的を理解した上で自社に合った導入方法を検討しなくてはいけません。 今回は働き方改革の背景と目的、導入方法や克服すべき課題を解説します。
2025年09月11日
業務用アルコールチェッカーの選び方|検知方式・形状タイプの違いを解説
アルコールチェッカーは、従業員の安全と法令遵守を確保する上で重要な役割を果たします。 本記事では、業務用アルコールチェッカーの選び方について、検知方式や形状タイプの違いを詳しく解説します。精度、携帯性、必要な機能、そしてメンテナンス頻度など、選定の際に考慮すべき重要なポイントを網羅的に紹介しています。 適切なアルコールチェッカーを選ぶことで、より効果的な飲酒運転防止対策を実現し、安全な職場環境の構築に貢献できます。
2025年11月05日
【2023年12月〜】アルコールチェック義務化に向けて企業が行うべき対策とは?
トラックやタクシーなどの緑ナンバー車両では、以前からアルコール検知器を使用したチェックが義務化されていましたが、2023年12月から、白ナンバー車両においてもアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。 そこで今回は、義務化の対象や背景、企業が取るべき行動について詳しく紹介していきます。おすすめのアルコール検知器についても併せてご紹介していますので、準備が必要な企業様はぜひ参考にしてみてください。 このような方におすすめです ・白ナンバー車両におけるアルコールチェックの義務化に関心がある方 ・2023年12月〜の義務化に向けてアルコール検知器を探している方 ・安全運転管理者責任者の責任範囲について詳しく知りたい方
2025年10月30日
サーマルカメラとは? 仕組みや特徴、おすすめの関連製品についてご紹介します
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、不特定多数の人が出入りするオフィスや商業/公共施設、イベント会場などで体温測定を行う機会が増加しており、その需要に応えるためサーマルカメラが注目されています。サーマルカメラは、赤外線センサーによって人体の表面温度を非接触で計測し、発熱者を早期に判別することができます。また、導入が容易であり、小規模な事務所や店舗でも利用されています。 そこで今回は、サーマルカメラの仕組みや特徴、おすすめの関連製品について紹介します。 ポイント ・新型コロナウイルスの感染拡大影響により需要増加のサーマルカメラ ・サーマルカメラの代表的な種類は「固定型・ハンディ型」「オンプレミス型・クラウド型」に分類される ・サーマルカメラのおすすめ関連製品をご紹介
2025年10月29日
業務用インカムの種類や選び方・導入前に知っておきたいこと
業務用インカムは様々な現場に広く普及し、業務効率化に貢献しています。本記事では、新しく業務用インカムの導入を検討されている方や、導入したが別製品への置き換えをご検討されている方向けに、業務用インカム選定において参考になる情報をご紹介します。
2025年09月08日
働き方改革で副業解禁が本格化。知っておきたい注意点とトラブルを防ぐ仕組みを解説
働き方改革では、各自が働く時間や場所などを自由に選択できる社会を目指しています。 働き方改革関連法には含まれていませんが、政府が推奨しているのが「副業・兼業の解禁」です。 2018年には厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表し、同じタイミングで「モデル就業規則」から副業禁止規則が削除されました。 働き方改革が推進されることで、会社以外での時間の過ごし方やキャリア形成が重要になっていくと考えられます。さらに2020年からコロナウイルス感染症拡大の影響で在宅勤務が増加したことで、労働者の副業への関心も高まっています。 働き方の選択肢が増える中で、企業も副業や兼業への方針や対策を検討する必要性が高まっている状況です。今回は、企業が副業・兼業を解禁する上で知っておきたい内容を解説していきます。
2025年09月05日
働き方改革にはDXが必要!「働き方改革」と「DX推進」でできること
・働き方改革とDXについての概要を知りたい ・働き方改革にDXがなぜ必要? ・DXを推進して働き方改革をする具体的な方法について知りたい このような疑問・悩みはありませんか。 DXは2018年に経産省がDX推進ガイドラインを公表、働き方改革は2019年に働き方関連法案の可決で共に、広く世間に浸透したバズワードです。 しかし、「DX」と「働き方改革」という言葉は聞いたことがあってもうまく説明できない方、DXと働き方改革の関係性、具体的なDX推進の方法について良く分からないという方も多いのではないでしょうか。 新型コロナウイルスの発生により人の生活・仕事は大きく変化しました。新型コロナウイルスがもたらした大きな環境の変化は「ニューノーマル」(新常態)として私たちの生活に浸透しています。リモートワークやデジタルの活用も当たり前になりました。 2023年3月13日に政府は、マスク着用を個人の判断に委ね、アフターコロナの変化の兆しも見えてきましたが、働き方改革とDXが未だ重要なことに変わりはありません。 本記事では働き方改革とDX推進についてのポイントや具体的な取り組み方についてご紹介します。 この記事の結論 ・働き方改革とは、多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革 ・DXとはデジタル技術を用いることでビジネスモデルそのものを変革すること ・IT関連のシステムを複合的に導入することでDX推進・働き方改革を実現できる ・技術の見本市エボルトでは働き方改革に役立つDX推進のシステムを紹介
2025年09月05日